マイホームは、ほとんどの人にとって、人生で一番大きな買い物と言えるでしょう。夢いっぱいの新生活、想像するだけでワクワクするものです。
しかし、ちょっと待ってください! 理想の立地や間取りも大切ですが、もっとも重要なのは「安全性」なんです。
どんなに素敵な家でも、もし災害に遭って家族や財産が危険に晒されてしまったら、元も子もありません。最近は、今まで安全だと思われていた場所でも、ゲリラ豪雨で浸水したり、土砂崩れが起きたり…。それに、日本は地震が多い国なので、どこに住んでいても地震のリスクはあると考えるべきでしょう。
「どこに住んでも何かしら心配はあるし…」とあきらめるのではなく、 大切なことは、リスクを理解し、自分たちが「これくらいなら大丈夫」と思える場所を選ぶことです。
そこで今回は、マイホーム購入検討者に向けて、知っておくべき主要な自然災害リスク、ハザードマップの活用法、物件探しの際の具体的な調査方法、リスクを考慮した物件選びのポイント、購入後の対策、そして適切な保険の選び方について、分かりやすく解説します。
ぜひ最後までお読みいただき、マイホーム購入にお役立てください。
知っておきたい!日本の主な自然災害リスク

まずは、日本で起こりやすい主な自然災害と、それが住まいにどんな影響を与える可能性があるのかをおさらいしましょう。
地震のリスク
日本は地震大国。建物が壊れるのはもちろん心配ですが、地面が液体のようになる「液状化現象」で家が傾いたり、地盤が沈んだりすることもあります。東日本大震災のとき、離れた千葉県で約26,000軒の戸建てが液状化の被害を受けました。
出典:一般財団法人消防防災科学センター 消防防災博物館 「東北地方太平洋沖地震による液状化被害の特徴」より
https://www.bousaihaku.com/wp/wp-content/uploads/2014/01/shikisya_wakamatsu.pdf
水害のリスク
最近、本当に多いのが水害です。大雨で川が氾濫する洪水のみならず、下水が溢れることにより発生する「内水氾濫」や、海沿いだと「高潮」にも注意が必要です。ハザードマップで予測されていたとおり、自宅が浸水したという事例は後を絶ちません。
土砂災害のリスク
山や崖の近くに住むときは、土砂崩れや地滑りが発生して、家が押し流されることがあります。一瞬で全てを奪ってしまう、非常に怖い災害です。
火山災害のリスク
活火山の近くでは、降ってくる火山灰のほか、火砕流のリスクもあります。日本では桜島や阿蘇山が活火山として有名です。
これらの災害は、家が壊れるのみならず、道路が使えなくなったり、電気や水道が止まったりして、私たちの生活そのものを大きく変えてしまう可能性があります。そのため、物件を選ぶときは、建物だけじゃなく、周りの環境も含めて、しっかりリスクを確認することが重要です。
強い味方!ハザードマップを使いこなそう
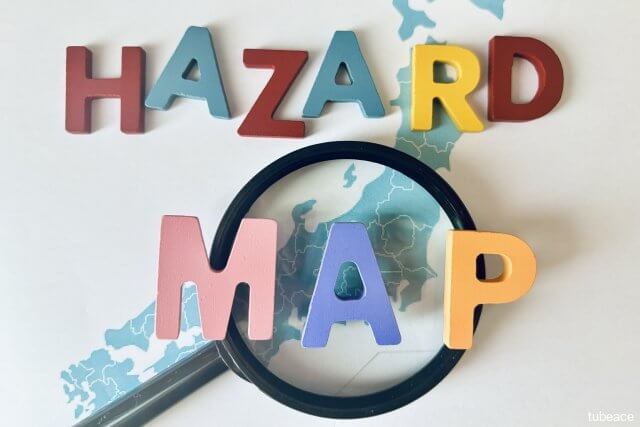
ハザードマップは、自然災害による被害予測を地図化したものであり、国土交通省の「ハザードマップポータルサイト」や各自治体のウェブサイトで閲覧可能です。
洪水ハザードマップ
浸水想定区域と浸水深が色分け表示されており、特に浸水深3m以上の区域では、2階への避難も困難となる場合があります。浸水継続時間も重要なポイントであり、長期にわたる浸水は建物の基礎に大きなダメージを与える可能性があります。
土砂災害ハザードマップ
「土砂災害警戒区域(イエローゾーン)」と「土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)」が表示されます。レッドゾーンは特に危険度が高く、新築には都道府県知事の許可が必要となる場合があります。
地震ハザードマップ
地震の揺れやすさや液状化危険度などが示されます。軟弱地盤(埋立地、旧河川跡地など)は、地震の揺れを増幅し、液状化リスクを高めるため、特に注意が必要です。
ただし、ハザードマップは予測に基づいているため、想定を超える災害が発生する可能性も否定できません。他の情報源と併せてリスク評価を行うことが重要です。
物件探しの時にできる!リスク調査のコツ

物件を選ぶときには、以下の方法を用いて災害リスクを調査することが可能です。
重要事項説明書
契約する前に、不動産屋さんから「重要事項説明書」という購入物件に関する詳細の説明の機会があります。重要事項説明書には、災害に関する大事な情報が書かれているので、しっかり確認しましょう。
・土砂災害の警戒区域に入っているか
・津波の警戒区域に入っているか
・浸水が予想される区域に入っているか
特に「過去の水害発生状況」は、実際に災害が起きた記録なので、参考にすべき情報でしょう。また、重要事項説明の内容で分からないことは、遠慮せずにどんどん質問するようにしましょう。
自分でできる!もっと詳しい調査方法
より詳細なリスク調査を行う方法として、まず国土交通省のハザードマップポータルサイトを活用することが挙げられます。このサイトでは、住所を入力するだけで、その場所における洪水、土砂災害、地震といった複数の災害リスクをまとめて確認することが可能です。
出典:国土交通省 国土地理院「ハザードマップポータルサイト」
https://disaportal.gsi.go.jp/
次に、自治体への問い合わせも有効な手段です。地元特有の災害情報に精通しているため、ハザードマップだけでは把握しきれないリスクを知ることができる場合があります。
また、実際に物件を訪れる際には、周辺環境を注意深く観察することが重要です。たとえ小さな川であっても、大雨によって氾濫する可能性があるからです。
周囲の土地よりも低い場所は水が集まりやすく、内水氾濫のリスクが高いと言えます。意外と信ぴょう性が高いのは、地元住民の声です。長年その土地で暮らしている人たちは、過去の災害経験や避難の様子など、具体的な情報を持っていることがあるため、地縁者の話を聞く機会があれば聞いてみてください。
リスクを考えて!賢い物件選びのポイント

災害リスクを踏まえ、安全性を重視した物件選びを行うためのポイントは以下の通りです。
建物の構造と耐震性能
新築物件では耐震等級を確認し、等級2以上が望ましいとされます。中古物件の場合は、建築年(1981年以前の建物は旧耐震基準)と、耐震診断・改修の有無を確認する必要があります。
土地の地盤と高さ
軟弱地盤は地震リスクを高めます。新築では地盤調査と改良工事が一般的ですが、中古物件では情報が不明な場合があります。周囲より高い土地は水害リスクが低く、避難経路も確保しやすい傾向があります。
避難の容易性
災害時の避難経路の確保も重要です。避難所までの距離や経路の安全性、幹線道路へのアクセス、高台や広場への避難経路、主要な病院などを確認する必要があります。また災害時に川を渡るのはリスクが高いため避けるべきです。橋を渡らないことを前提とした避難計画を立てておきましょう。
ライフラインの復旧性
都市部はライフラインの復旧が比較的早い一方、山間部や島嶼部は遅れる可能性があります。集合住宅では、建物被害による供給遅延も考慮する必要があります。地方都市では、プロパンガスや浄化槽が多い傾向にありますが、これらの設備は個別に設置されるものであるため、災害時でも利用しやすいというメリットがあります。
購入後のリスク軽減策はどうしたらいい?

物件購入後も、災害リスクを軽減するための対策を講じることは非常に重要です。これまで紹介してきたのは、あくまでも災害リスクが少ない立地や復旧可能性の高い物件選びのポイントでした。しかし、災害リスクの軽減は物件は購入してからが本番です。
以下では、物件購入後にやっておきたいリスク軽減策を解説します。
地震に対しては、中古物件の場合、まず耐震診断を受け、その結果に基づいて耐震補強工事を検討することが有効です。また、家具の転倒防止措置や窓ガラスの飛散防止フィルムの利用も、比較的容易にできる対策として挙げられます。間取りと家具の配置の関係では、寝室などには大型家具を設置しない、家具に転倒防止策(突っ張り棒など)を施すといった工夫も効果的です。
水害のリスクがある地域では、止水板や土のうを準備しておくこと、電気設備を可能な限り高い位置に設置すること、そして排水溝や雨どいを定期的に清掃することが効果的です。さらに、避難警報が発令されたときには、ためらうことなく避難するという意識を家族間で共有しておくことが、被害を最小限に抑えるために不可欠です。
水害は想像以上の被害をもたらすことがあります。そのため、自宅を新しく建築するときは基礎を上げるなどの工夫も被害を抑える役割を持つでしょう。また、想定以上の降雨が発生すると雨樋の処理能力を超えてしまうため、雨樋から溢れた雨が建物内に侵入する可能性もあります。雨樋を処理能力の高いものに交換することで、建物へのダメージを最小限に抑えることが可能です。
地震後の火災に備えては、感震ブレーカーの設置や消火器の準備に加え、定期的な避難訓練を実施することが重要となります。
保険の選び方はどうすればいい?
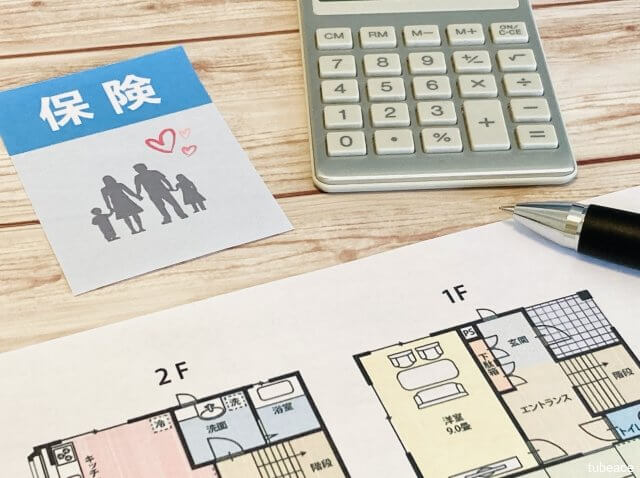
災害に備えるためには、火災保険が欠かせません。しかし、どのような保険に入ればよいのか、どのようなポイントを重視すればよいのか、非常に難しい問題です。
ここでは、一般的な「火災保険」のアウトラインについて解説します。
火災保険では、火災、風災、雪災といった基本的な補償に加え、近年増加傾向にある水害リスクを考慮し、水災補償を必ず検討すべきです。ただし、水災リスクの高いエリアにおいては、保険料が高額になる場合や、補償内容に制限が設けられることがある点に留意が必要です。また、逆に水災リスクの低い(もしくは考えられない)エリアでは、水災補償を外す、もしくはリスクを低く評価して保険料を安くする方法もあります。
また、地震による損害は火災保険ではカバーされないため、地震保険も検討する必要があります。地震保険は火災保険とセットで加入する必要があり、建物の再建築費用を考慮して保険金額を設定することが重要です。
そのほか、天災リスクの話とは逸れますが、火災保険では天災のほか「不測突発的な事故」も補償されます。
・子どもが室内のテレビを引き倒してしまいテレビを修理(購入)する必要が生じた
・部屋のなかでつまずいてしまい、建具を破損させてしまった
このような日常生活で発生しうる「小さなリスク」も実は保険での対応が可能です。天災リスクへの対応はほとんどの保険会社でカバーできるため、このような不測突発的な事故の対応可否や補償内容をもって保険を選ぶのも、有効な選択肢です。
なお、火災保険の内容は各社によって大きく異なります。複数の保険会社から話を聞くなどして、その内容をよく理解し、最適な保険契約を見つけることをおススメします。
未来の安心への投資

マイホームは、人生で最大のお買い物。だからこそ、後悔しないために、災害のリスクを理解して、安全な場所を選ぶことが、家族の笑顔を守るためにも非常に重要です。
ハザードマップを見たり、不動産会社に説明を求めたり、内見時に周りの状況をチェックしたり。めんどくさいと考えるかもしれませんが、事前にできることはたくさんあります。
完全に安全な場所はないかもしれませんが、リスクを知って、自分たちが納得できる範囲で物件を選ぶことが大切です。そして、購入した後も、自分でできる備えをしっかりしておくことで、万が一の時にも、被害を最小限に抑えることができます。
災害に備えた住まい選びは、未来の安心への投資です。
この記事が、これからマイホームを探すみなさまのお役に立てたら嬉しいです。


